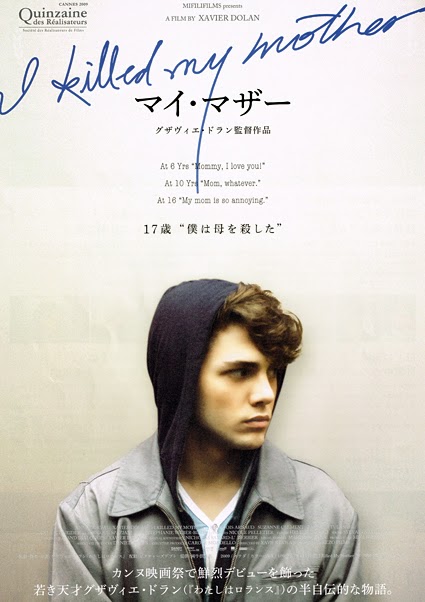町山智浩さんの『トラウマ映画館』が好きで(本もトラウマ映画のレビューも)最近Podcastで「町山智浩のアメリカ映画特電」という話が面白くてちびちび聞いている。それで、本屋でこのブレードランナーの未来世紀を見つけたので買って読んでみた。 この本で章立てられている映画は、 デヴィッド・クローネンバーグ『ビデオドローム』 ジョー・ダンテ『グレムリン』 ジェームズ・キャメロン『ターミネーター』 テリー・ギリアム『未来世紀ブラジル』 オリヴァー・ストーン『プラトーン』 デヴィッド・リンチ『ブルーベルベッド』 ポール・ヴァーホーヴェン『ロボコップ』 リドリー・スコット『ブレードランナー』 の8本である。しかし、この映画たちのもとになった映画、今後影響を与えることになった映画など、この8本以外にもたくさんの映画が本書の中で紹介される。 町山智浩さんの本でも話でも共通することなんやが、紹介される1本の映画の中から関連する他の作品を次々と挙げていって、どういった映画が元になているのかや、監督や役者の性格や嗜好など大変細かい所まで分析されていて、それをPodcastでは、面白そうに話されるのでそれがまた面白い。この映画見たいな、と思ってしまう。そういった面から考えると、私は町山さんの本も好きだが、Podcastみたいに話してる話を聞くほうが好きなのかもしれない。映画をあまり見ないパートナーも町山さんのPodcast好きなので(というかおもろいとむしろ教えてもらった)話術がおもろいんやと思う。 この本の中でやったらビデオドロームが1番好きやから、そこを特に興味深く読んだのだけれども、監督の熱い想いまで強く解説してくれていて、とても面白い本だった。タイトルの通り、映画の見方が今までと変わっていく本。 町山智浩 〈映画の見方〉がわかる本 80年代アメリカ映画カルトムービー篇 ブレードランナーの未来世紀 (2006年、洋泉社) <楽天市場>【送料無料】 ブレードランナーの未来世紀 “映画の見方”がわかる本 80年代アメリカ映画カル... 価格:1,728円(税込、送料込)